「犬 手作り ご飯 保存 容器」で検索しているあなたへ。愛犬に手作りご飯をあげるなら、保存方法や容器の選び方はとっても大事ですよね。
この記事では、保存容器の選び方や冷蔵・冷凍の基本ルール、ご飯の量の目安までわかりやすく紹介します。人気のレシピや、やってはいけない保存例、冷凍向きの食材、老犬向けの簡単レシピなどもぎゅっとまとめました。
さらに、ご飯の量をパッと計算できるアプリも紹介しているので、毎日のごはん作りがラクになりますよ。
- 犬の手作りご飯に適した保存容器の素材と特徴
- 冷蔵・冷凍それぞれに合った保存方法のポイント
- 食材の選び方や冷凍に向く食材の種類
- 手作りご飯の適切な量や管理方法
犬の手作りご飯を保存する容器の選び方

手作りご飯の保存容器の選び方
犬の手作りご飯を安全に保つためには、適切な保存容器の選定が欠かせません。どんな容器を使うかによって、鮮度や衛生状態が大きく変わります。
まず注目したいのは、素材の違いです。一般的に使われる素材はプラスチック、ガラス、ステンレスの3種類です。以下の表で特徴を比較してみましょう。
| 素材 | 特徴 | 向いている用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| プラスチック | 軽くて扱いやすい、安価 | 冷蔵保存向け | ニオイ移りや変色に注意 |
| ガラス | 匂い移りが少ない、耐久性が高い | 冷蔵・冷凍両方に対応可能 | 割れやすく重たい |
| ステンレス | 衛生的で丈夫、温度変化に強い | 冷凍保存や長期保存に適している | 中が見えないため管理に工夫が必要 |
このように見ると、冷蔵保存にはガラスが、冷凍保存にはステンレスが適しているケースが多いといえます。ただし、容器のサイズやフタの密閉性も重要です。特に冷凍保存の場合、しっかりと密閉できないと霜がついたり風味が落ちる原因になります。
このため、購入前には「電子レンジ対応か」「食洗器で洗えるか」といった日常の使いやすさも確認しましょう。冷凍・冷蔵どちらに保存するかを決めた上で、保存期間や回数に応じた容器選びをすると無駄がありません。
国産フードで唯一のすっぽん配合【ミシュワンシニア犬用ドッグフード】手作りご飯の保存方法の基本
犬の手作りご飯を安全に保管するには、冷蔵・冷凍を使い分けることが基本となります。作ったご飯をすぐに与えない場合、常温放置は避けなければなりません。
まず、冷蔵保存は作ったその日のうちに食べる予定のご飯に適しています。保存期間の目安は最大でも2日以内。それ以上置くと、酸化や雑菌の繁殖リスクが高まります。
一方で、冷凍保存は1週間分ほどまとめて作り置きしたい場合に便利です。冷凍する際は1食分ずつ小分けにして、できるだけ空気を抜いて密閉保存することで、冷凍焼けや味の劣化を防げます。温め直す際は電子レンジを使っても問題ありませんが、「人肌程度までしっかり冷ます」ことが大切です。
ここで注意すべきは、再冷凍を避けることです。一度解凍したものを再び冷凍すると、食材の質が落ちるだけでなく、衛生的にもリスクが伴います。
こうして、「作る→冷凍→解凍→すぐ与える」という明確な流れを守ることが、手作りご飯を安全に与える上でのポイントとなります。
手作りご飯の量の目安と管理

犬の健康を守るためには、手作りご飯の量を正確に把握することが大切です。見た目や感覚だけに頼ると、肥満や栄養不足の原因になることがあります。
まず基本となるのは、「犬の体重 × カロリー計算式」です。一般的な目安として、以下の式がよく使われます。
【必要カロリー】=体重(kg)×30+70
たとえば体重5kgの成犬であれば、
5×30+70=220kcalが1日の目安となります。
しかし、これはあくまで基準値であり、犬の年齢・活動量・体質によって調整が必要です。下の表に、犬のタイプ別の注意点をまとめました。
| 犬のタイプ | カロリー調整のポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 子犬 | 基準の2倍まで必要になることがある | 成長期はエネルギー消費が多い |
| シニア犬 | 活動量が減るため基準の80〜90%程度が目安 | 消化に優しいメニューを意識 |
| 去勢・避妊後 | 太りやすくなるため控えめに | 高カロリー食材は減らす |
日々の管理には、犬用の体重管理アプリや食事記録ノートを活用すると便利です。アプリの中には、体重と年齢を入力するだけで自動で1日の給餌量を計算してくれるものもあり、初めて手作りご飯に挑戦する飼い主にもおすすめです。
過剰摂取を防ぐためには、与えたご飯の**「総重量」と「主な食材」**を記録する習慣をつけましょう。手作り食はドライフードと異なり、水分量や食材ごとのカロリーがバラつくため、数値で管理することがとても重要です。
人気のある犬の手作りご飯レシピ
犬の手作りご飯で人気なのは、消化がよくて栄養バランスの取れたレシピです。特に家庭で手に入りやすい食材を使ったメニューが好まれています。
ここでは、代表的なレシピを3つ紹介します。
| レシピ名 | 主な食材 | 特徴 |
|---|---|---|
| 鶏むね肉と野菜のおじや | 鶏むね肉・にんじん・かぼちゃ・白米 | 低脂肪で消化しやすく、初心者に人気 |
| 鮭とさつまいもの煮込み | 鮭・さつまいも・ブロッコリー・キャベツ | アレルギー対策にもなる魚ベース |
| 豚ひき肉と豆腐炒めごはん | 豚ひき肉・豆腐・小松菜・押し麦 | タンパク質と食物繊維が豊富 |
これらのレシピは、いずれも味付けを一切行わないことが基本です。人間用の調味料は犬にとって危険な成分を含む場合があるため、無添加・無香料・無塩分が鉄則です。
また、季節や犬の体調に合わせて野菜の種類や肉の部位を変えるのも良い工夫です。例えば、夏場は水分の多い「きゅうり」や「ズッキーニ」を取り入れると、水分補給にも役立ちます。
手作りご飯を長く続けるには、簡単・作り置き可能・食材アレンジが効くという3つの要素を意識すると、飼い主の負担も減ります。調理法に慣れてきたら、犬の好みや体調に合わせてオリジナルレシピを作ってみるのもおすすめです。
関節サポート配合サプリメントいらず手作りご飯でよくない保存例

犬の手作りご飯を安全に与えるには、保存方法を間違えないことが前提です。誤った保存は、食中毒や栄養劣化の原因になりかねません。
以下は、避けるべきよくない保存方法の例です。
| よくない保存例 | 問題点 | なぜNGか |
|---|---|---|
| 常温で半日以上放置したご飯 | 雑菌が繁殖しやすい | 特に夏場は1~2時間で腐敗が始まることも |
| 人間用の味付け容器に一緒に保存 | 塩分・調味料が混入する可能性 | 犬には有害な成分が付着するリスク |
| 冷蔵庫で5日以上保存したご飯 | カビ・腐敗が進行 | 冷蔵は3日以内が安全な目安 |
| 解凍後の再冷凍を繰り返す | 味と栄養が劣化、衛生面も不安 | 一度解凍したら使い切るのが基本 |
| ラップだけで冷凍保存したご飯 | 乾燥や冷凍焼けを起こしやすい | 密閉容器やジップ袋の使用が望ましい |
このような保存ミスを防ぐには、冷蔵3日・冷凍2週間以内を目安とし、1回分ごとに小分けしておくと便利です。さらに、保存容器には犬用に使い分けた清潔な専用容器を使うことも忘れずに。
一見些細なことでも、犬の体には大きな影響を与えるため、保存状態のチェックは毎回行う習慣をつけることが重要です。
手作りご飯の味付けで注意する点
犬の手作りご飯においては、味付けをしないことが鉄則です。人間にとって美味しい味は、犬にとって過剰な塩分・脂質であることがほとんどだからです。
まず避けるべきは以下のような代表的なNG食材・調味料です。
| 食材・調味料 | 問題点 | 備考 |
|---|---|---|
| 醤油・味噌 | 塩分過多 | 腎臓に大きな負担をかける |
| 玉ねぎ・ねぎ類 | 中毒性があり、赤血球を壊すことも | 加熱しても毒性は消えない |
| にんにく | 少量でも体調不良の原因に | 体重によっては命に関わることも |
| 砂糖・はちみつ | 虫歯や糖分過多につながる | 特に子犬やシニア犬は要注意 |
また、だしやスープも市販品は要注意です。たとえ「無添加風」に見えても、隠れた塩分や保存料が入っている場合があります。使うなら、鶏のゆで汁など、家庭で無塩で取ったものに限りましょう。
「美味しく食べてほしいから味をつけたい」と思っても、犬の味覚は人間とは異なります。素材そのものの香りや食感を楽しむ性質があるため、味付けは不要どころか健康リスクに直結します。
このように、安全な手作りご飯のためには“味付けしないこと”が最大の配慮となります。特に初めて手作りご飯に挑戦する飼い主は、無味でも犬は十分に喜ぶことを知っておくと安心です。

犬の手作りご飯に適した保存容器と冷凍方法

手作りご飯レシピに使う冷凍向き食材
犬の手作りご飯をまとめて作って冷凍保存する場合、使用する食材の選び方が重要です。冷凍に向かない食材を使うと、解凍時に水っぽくなったり、風味が落ちたりして、犬が食べなくなる可能性があります。
ここでは、冷凍に向く食材と向かない食材を一覧でまとめます。
| 分類 | 冷凍向き食材 | 冷凍に向かない食材 |
|---|---|---|
| 肉類 | 鶏むね肉、ささみ、豚ひき肉、牛赤身 | 加熱後の脂身が多い部位 |
| 魚類 | タラ、サーモン、アジ(骨なし) | 水分が多すぎる白身魚(例:しらす) |
| 野菜類 | にんじん、かぼちゃ、さつまいも、ブロッコリー | レタス、きゅうり、トマト |
| 炭水化物 | 白米、さつまいも、じゃがいも(マッシュ) | 冷やご飯や硬めに炊いたご飯 |
| その他 | 卵(炒り卵や茹で卵)、豆腐(軽く水切り) | 生卵そのまま、豆腐のまま(崩れやすい) |
冷凍に向く食材は、しっかり加熱してから冷凍することが基本です。とくに肉や魚は、中心まで火を通した状態で保存しましょう。
また、冷凍する際は、食材を細かく刻んだり、マッシュ状にしておくと解凍後も食感が損なわれにくくなります。小分けにして冷凍すれば、毎回解凍する量も適切に調整できます。
冷凍保存のコツは、「風味の劣化を最小限に抑える」ことです。そのため、ラップ+ジッパー袋、または密閉容器を活用して、空気に触れないように保存するのがポイントです。
ネルソンズドッグフード老犬向けの簡単な手作りご飯レシピ
老犬になると、消化機能や噛む力が落ちてきます。そのため、やわらかく消化しやすい食材を中心にしたレシピが適しています。ここでは、1食分を約10〜15分で作れる簡単レシピを紹介します。
【やわらか鶏雑炊レシピ】
- 材料(1食分)
- 鶏むね肉(皮なし・細かく刻む) 40g
- 白米(やわらかめに炊く) 50g
- にんじん(すりおろし) 10g
- かぼちゃ(マッシュ) 10g
- 水 100ml
- 作り方
- 鶏むね肉を一度茹でて、細かくほぐします。
- 白米とすりおろし野菜、マッシュかぼちゃを鍋に入れて水で煮込みます。
- 全体がとろとろになったら火を止めて、粗熱を取ってから与えます。
このようなレシピは、歯が弱くなった老犬でも食べやすく、栄養のバランスも良好です。とくに野菜をすりおろすことで、吸収効率が高まり、胃腸への負担が軽減されます。
また、シニア犬は腎臓や肝臓の機能が低下していることが多いため、塩分や脂肪は極力控えるようにしましょう。味付けはもちろん不要です。
もし水分摂取が不足気味であれば、鶏の茹で汁を薄めて使うことで香りが立ち、水分補給にもつながるのでおすすめです。
手作りご飯に使う野菜の選び方

犬の手作りご飯に使う野菜は、種類と調理法の選び方が重要です。人間にとって健康的な野菜でも、犬にとっては負担になる場合があります。
まず避けたいのは、ネギ類(玉ねぎ・長ネギ・ニラ)やアボカドなどの中毒を起こす野菜です。これらは少量でも危険なので、絶対に使用しないようにしましょう。
一方で、犬のご飯に適した野菜には以下のようなものがあります。
| 種類 | 調理のポイント | 主な栄養と効果 |
|---|---|---|
| にんじん | 茹でてすりおろすと消化しやすい | βカロテンで抗酸化作用が期待できる |
| かぼちゃ | 蒸してマッシュすると食べやすい | 食物繊維とビタミンEが豊富 |
| キャベツ | 茹でて細かく刻む | ビタミンCで免疫サポート |
| 小松菜 | アク抜きして加熱、刻んで使用 | 鉄分・カルシウムで骨と血液の健康 |
| ブロッコリー | 軸もやわらかく茹でればOK | 抗酸化物質と胃腸の調整効果 |
このように、加熱と刻み方を工夫することで、多くの野菜が使えるようになります。また、野菜は生よりも必ず加熱してから与えるようにしてください。加熱することで、消化吸収がよくなり、胃腸への負担を減らすことができます。
特に初めての野菜を使うときは、一種類ずつ少量から始めて様子を見るのが基本です。
手作りご飯に白米を使う際の工夫
白米は犬にとってエネルギー源として優れた食材ですが、炊き方や混ぜ方に工夫が必要です。適切な使い方をすれば、毎日の手作りご飯をより栄養バランスの取れたものにできます。
まず、炊き方については、柔らかめに炊くのが基本です。通常より水分を多めにし、消化しやすいようにすることが大切です。固めに炊いた白米は、犬の胃腸には負担がかかります。
また、白米だけでは栄養バランスが偏るため、肉や野菜と組み合わせて使うことが基本です。たとえば、以下のような配分が理想的です。
| 食材 | 目安の割合(体重や年齢により調整) |
|---|---|
| 白米 | 約30〜40% |
| 動物性たんぱく(鶏肉など) | 約40〜50% |
| 野菜類 | 約10〜20% |
さらに、冷凍保存に向けた工夫として、白米はマッシュ状にしておくと解凍後も食感が保たれやすくなります。その際、他の食材と混ぜてから冷凍することで、毎回の準備が簡単になります。
ご飯の香りが落ちるのを防ぐには、冷凍前にラップで包み、密閉容器で保存するのが効果的です。

手作りご飯の量を計算できるアプリ

犬の手作りご飯を毎日与える際に「どれくらいの量を用意すればいいのか」と迷う方は多いはずです。そんな時に役立つのが、手作りご飯の給餌量を計算できるアプリです。
最近では、犬の体重や年齢、活動量を入力するだけで、1日に必要なカロリーや食事量の目安を提示してくれるアプリがいくつか登場しています。
主な機能や特徴を比較すると、以下のようになります。
| アプリ名 | 特徴 | 対応OS |
|---|---|---|
| Petly(ペットリー) | 栄養計算+献立提案機能つき | iOS・Android両対応 |
| ワンごはん計算アプリ | 手作りご飯の量計算に特化 | Androidのみ |
| DogCal(ドッグカル) | 毎日のカロリーと運動量まで管理可能 | iOSのみ |
これらのアプリを使えば、「何gの肉」「どのくらいの白米」といった細かい量まで把握でき、健康管理の精度が上がります。また、過去の食事記録を保存しておけるアプリもあり、継続的な健康チェックに役立ちます。
ただし、あくまで目安の数値ですので、体調の変化や食べ残しの有無に応じて微調整することが必要です。特に成長期や老犬では、かかりつけ獣医の意見も併せて参考にするとより安心です。
プレミアムドッグフード『モグワン』犬の健康を守るための犬の手作りご飯を保存する容器の総まとめ
- 保存容器はプラスチック・ガラス・ステンレスの3種類が主流
- 冷蔵保存にはガラス容器が適している
- 冷凍保存にはステンレス容器が向いている
- プラスチックは軽量で扱いやすいが臭い移りに注意
- 容器の密閉性が保存の鮮度と衛生に直結する
- 電子レンジ対応かどうかは事前に確認すべき
- 食洗機で洗える容器は衛生管理がしやすい
- 保存方法は冷蔵と冷凍を使い分けるのが基本
- 冷蔵保存は最大2日までが安全な目安
- 冷凍保存は1食分ずつ小分けして空気を抜いておく
- 再冷凍は品質と衛生を損なうため避けるべき
- ご飯の量は犬の体重×30+70でおおよそ算出できる
- 子犬・老犬・避妊後などは摂取量に個別調整が必要
- 白米は柔らかく炊いて他の食材と組み合わせて使う
- 味付けは一切不要で、調味料や有害食材は厳禁
- 保存容器の管理と食材の冷凍適性が保存品質を左右する
- 給餌量の計算には専用アプリの活用が便利である
- 老犬にはやわらかく消化しやすいレシピを選ぶべき
- 手作りご飯に使う野菜は加熱と刻み方が消化の鍵
- 保存に失敗すると健康リスクが高まるため管理が重要

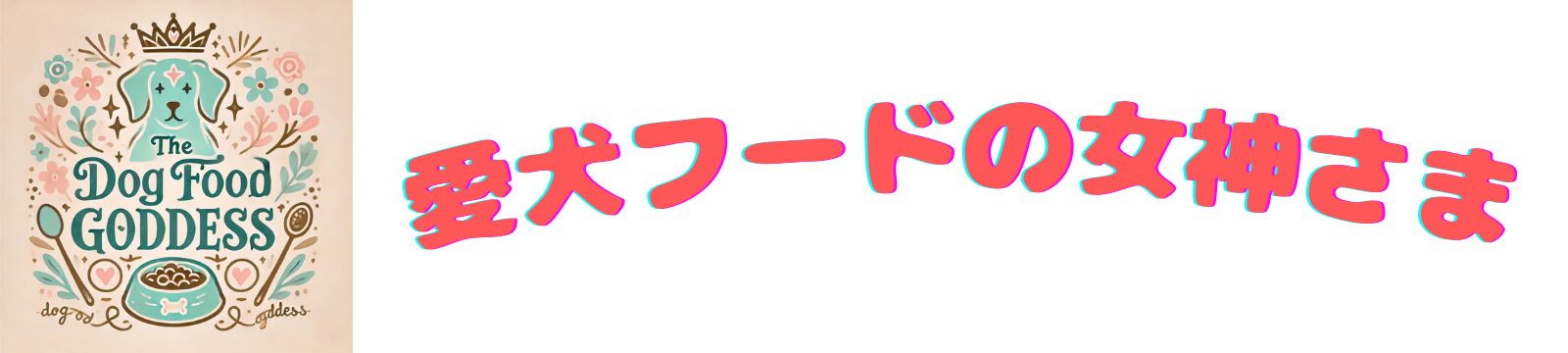

コメント